

- 2008年度 ・第7期 入塾式
- 男子・ステージ別
-
- 第01ステージ|03月21日?23日
- 第02ステージ|04月04日~06日
- 第03ステージ|04月18日~20日
- 第04ステージ|05月02日?04日
- 第05ステージ|05月16日?18日
- 第06ステージ|05月30日?06月01日
- 第07ステージ|06月13日?15日
- 第08ステージ|06月27日?29日
- 第09ステージ|07月11日?13日
- 第10ステージ|07月25日?27日
- 第11ステージ|08月08日?10日
- 第12ステージ|08月29日?31日
- 第13ステージ|09月12日?14日
- 第14ステージ|09月26日?28日
- 第15ステージ|10月10日?12日
- 第16ステージ|10月24日?26日
- 第17ステージ|11月07日?09日
- 第18ステージ|11月21日?23日
- 男子・チーム別
- 女子・ステージ別
-
- 第01ステージ|03月28日?30日
- 第02ステージ|04月11日?13日
- 第03ステージ|04月25日?27日
- 第04ステージ|05月09日?11日
- 第05ステージ|05月23日?25日
- 第06ステージ|06月06日?08日
- 第07ステージ|06月20日?22日
- 第08ステージ|07月04日?06日
- 第09ステージ|07月18日?20日
- 第10ステージ|08月01日?03日
- 第11ステージ|08月22日?24日
- 第12ステージ|09月05日?07日
- 第13ステージ|09月19日?21日
- 第14ステージ|10月03日?05日
- 第15ステージ|10月17日?19日
- 第16ステージ|10月31日?11月02日
- 第17ステージ|11月14日?16日
- 第18ステージ|11月28日?30日
- 女子・チーム別
- 2008年度 ・第7期 卒塾式
![]() (市村自然塾 関東 OB会)
(市村自然塾 関東 OB会)
ステージテーマ:「作物の生育状況を観察し、適切な世話をしよう!」
共同生活の目標:「何事も心を込めて、きちんと丁寧に作業する」
第5ステージまでにジャガイモ・ゴボウ・キャベツ・レタス・ダイコンなど様々な作物の植え付けや種まきを行ってきました。
天候不順のため残念ながらスタッフが植え付けを行ったものもありますが、第6ステージではそれらの作物も含め、それぞれの作物に適切な世話を行いました。
今ステージも天候不順で世話ができなかった作物がありますが、室内で作物の種類・生育段階によってどのような世話をすればいいのか学習したり、普段使っている道具の手入れについて学びました。
共同生活の目標は「何事も心を込めて、きちんと丁寧に作業する」を掲げ、農作業や清掃をはじめ1つ1つの作業に意識して取り組んでもらいました。
■ 06月06日:夜の集い
ステージを始めるにあたり、塾頭からお話をいただきました。
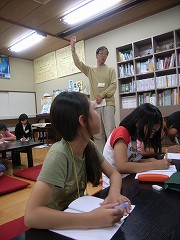
「皆さんが入塾してから3分の1が経ちました。農作業や掃除など一通りのことをやりましたが、ただやるだけでなくいろいろなことに気付き、感じてください。これから言う4つのことをできるようになって欲しいと思います。1つ目は自分勝手な行動はしない。2つ目は仲間を大切にし、協力する。3つ目はあいさつ・時間を守るなど当たり前のことを当たり前にする。4つ目は自分から進んでする。今まで感じていなかった人はこれから残りのステージで感じてください。そして自主性を持って、自律した人間になってください。自分に強い人間になってください。」
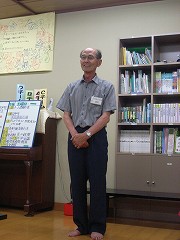
また、このステージには市村自然塾 九州から塾頭の金丸さんが見学にいらっしゃいました。
このあと第3ステージのマナー講座を振り返り、自分自身でどれくらい守れているのか確認する時間もありました。◎、○、△、×の4段階で評価してもらいましたがほとんどの塾生が◎や○という評価でした。みんなで選んだマナーです。これからもしっかり守りましょう。
■ 06月06日:食事当番

翌朝の釜飯炊きの準備で米とぎをしています。お米を1粒も流さないように真剣です。自然塾だけでなく、家でもお手伝いできるといいですね。
■ 06月07日:あしおとツアー ?夏野菜の芽欠き・誘引・追肥?
女子塾生が植え付ける予定だった夏野菜は、天候不順のため代わりにスタッフが植え付けをしました。そのため、女子塾生が夏野菜に触れるのは今回が初めてでした。

写真はトマトのわき芽を欠きとっているところです。わき芽を放っておくとどんどん育ち、風通しが悪くなる原因になったり、わき芽が伸びるのに余分なエネルギーを使ってしまうので、小さいうちに取り除きます。

トマト・ナス・ピーマンのわき芽を取り除いたら、誘引をしました。誘引とは株が倒れないように支柱と結びつけてあげる作業です。女子塾生は初めての作業で、スタッフに教わりながらも8の字に結びつけるのに苦戦していました。

これからもっと大きく、太く成長するので、茎の周りをきつく締めすぎないように結んであげましょう。真剣に結び付けているのが伝わってきますね。
■ 06月07日:あしおとツアー ?ゴボウの土寄せ・種まき?

おやつを挟んで、ゴボウの世話をしました。スタッフが追肥を行ったところへ土寄せを行いました。
女子塾生のゴボウの畝には、発芽しなかったのか、ヨトウムシにやられてしまったのかは、はっきりとはわかりませんが、、芽が出ていない場所が多いので追加の種まきをしました。 今回は今の時期に播いても収穫が間に合うサラダゴボウという品種を播きました。作物を育てるのは簡単ではないことを身を持って学べたのではないでしょうか。

今年は雨が多く、以前播いた卵の殻が流れてしまったので、残っている株の根元に塾生が播き直しました。ゴボウの芽にかからないように丁寧に播きました。
■ 06月07日:チーム農園作業
今ステージも各チームともにやらなければならない作業がたくさんありました。新しい作物の植え付けをする人、畑にある作物に必要な世話をする人、雑草を除去する人といったようにしっかりと役割分担をして作業に取り組んでいました。

このチームでは午前中に学んだ夏野菜の世話(トマトの芽欠き)を実践していました。しっかりとわき芽を見分けて欠きとっていました。

このチームはポットに播いたラッカセイが大きく育ったので畑に植え付けました。何か網みたいなものをかけていますね。
これはハクビシン対策です。ラッカセイは地下に実がなるので、ハクビシンが食べてしまわないように金網で覆って防ぎます。

畑の作物に負けないくらい雑草もぐんぐん成長しています。このチームは慣れない鎌を使いながら、畑の周りの雑草もしっかりとっていました。これからチーム農園でも共同農園でもますます雑草との格闘が増えていきます。

間引きで抜いたものですが、もう立派なカブの形になっています。このチームは早速お土産に持って帰りました。
■ 06月07日:あしおとツアー ?レタス収穫・キャベツの虫取り・防除液まき?

第3ステージに植え付けをしたレタスが大きくなり、お土産としてに収穫しました。きれいに巻いていて、おいしそうですね。
第1ステージ以降に塾生が植え付けた作物の中では最初のお土産となりました。

次に同じく第3ステージに植え付けをしたキャベツの世話をしました。
写真はキャベツについているアオムシをピンセットで1匹づつ取っている様子です。中にはアオムシに食べられて穴だらけのキャベツもありました。

その後、防除液(唐辛子やニンニクを漬け込んだ焼酎・木酢液・酢・水を混ぜ合わせた自然農薬)をまきました。
■ 06月07日:星の観察会
夜の塾活動では天気がよければ外で星の観察会をする予定でしたが、生憎の曇空で星が見えませんでした。せっかくボランティアの先生にお越しいただいたので、室内で肉声解説付のプラネタリウムや月の満ち欠けの実験を行いました。

月の模型をぐるりと囲んで輪になり、塾生にそれぞれ自分から見える月の形をスケッチしてもらいました。そして、そのスケッチを中央に並べ、同じ月の模型を見ていても場所によって見え方が違うことを全員で確認しました。

写真は日食の実験をしている様子です。次に日本で日食が見られるのは来年の7月です。

最後にあしおとだよりと一緒に送った星に関するクイズの回答をしていただきました。
プラネタリウムの途中や、星のシュミレーションを映し出している時にも塾生から多くの質問が出ましたが、ボランティアの先生はどの質問にも丁寧に答えてくださいました。この経験は塾生にとってよりいっそう星に興味を抱くきっかけとなったと思います。
■ 06月08日:季節の話・朝の瞑想

毎回日曜日の朝に季節の話と朝の瞑想を行っています。季節の話は"麦秋至(ばくしゅういたる)""芒種(ぼうしゅ)"についてお話しました。"麦秋至"とは麦が黄金色になり麦畑が秋のようになる頃という意味で麦を収穫する頃を指しています。"芒種"とは稲の種まきをする頃を指しています。
瞑想は、だいぶ慣れてきたようで最後まで動かずに背筋をピンとしていられる塾生が増えてきました、しかし途中でそわそわと動き出してしまう塾生もまだいます。しっかりと心を落ち着かせて、自分に対する強さを持ってください。
■ 06月08日:作物の生育段階に応じた様々な世話の話・鎌研ぎ
第5ステージに行えなかったラッカセイの種まきとダイコンの世話をする予定でしたが、あいにく朝から雨が降ってしまったため、作物の生育段階に応じた様々な世話の話と、鎌研ぎの作業に分かれて交代で行いました。

道具を長く使うには手入れは欠かせません。鎌を研ぐ作業はどの塾生も初めてでしたが説明を聞き、真剣に取り組んでいました。鎌はこれから頻繁に使います。しっかりと手入れをして大切に使いましょう。

室内では葉菜類・根菜類・果菜類それぞれの育て方の違いを具体例を挙げながら説明してもらいました。写真は作物の栄養状態を見極めるためのチャートを披露しているところです。

説明を聞いてしっかりと塾生手帳に記録していますね。ここで学んだことを、チーム農園で生かしていきましょう。
■ 06月08日:ステージのまとめ・振り返り
ステージの終わりに塾頭さんからお話がありました。
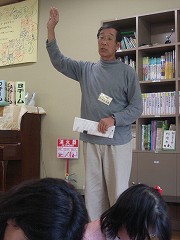
「人は一人では生きていけません。お互い助け合って生きています。塾でも世の中でもそうです。皆さんは"情は人の為ならず"という言葉を知っていますか?親切なことをすると必ず自分に返ってくるという意味です。そこで皆さんにお願いしたいのが、人間として基本的なことを大切にすることです。基礎がしっかりしていれば勉強など様々なことがしっかり身につくようになります。
また、なぜ自分からやることが大切かというと、相手の痛み、大変さというのは頭で考えただけではわかりません。自分で経験することで初めてわかるからです。これらのことを心がけて残り3分の2を取り組んでください。」
■ 編集後記
女子ステージでは珍しくすべての作業ができるかな?と思っていたのですが、日曜日に雨が降ってしまいました。雨が降ったことは残念でしたが、チーム農園の時間がしっかりとれたことは良かったと思います。また雨だからこそできることもあります。
今回行った鎌研ぎもその一つです。道具の手入れというのは道具を長持ちさせるためにとても大切なことです。今は何でも使い捨ての時代になってしまい、壊れてしまったり、いらなくなったらすぐに捨ててしまう人も少なくありません。以前塾頭のお話にもありましたが、道具は自分を手助けしてくれるものです。だからこそ大切に使わなければならないし、大切に使えば自分の腕もあがります。またこの話は、今回の共同生活の目標「何事も心を込めて丁寧に作業する」にも繋がってきます。心を込めて丁寧に作業できる人はものも大切にできます。ものを大切にする心がある人は人も大切にできます。皆さんはしっかりと意識して行動できているでしょうか。塾だけでなく日々の生活の中でも意識してもらいたいと思います。
K.T.

ほかにもイロイロあんなこと、こんなこと。自然塾豆知識コーナー