| 2012.10.05~07 | |
| 第14ステージ ~女子~ | |
| ステージテーマ:「コンニャク作りを体験し、先人の知恵を学ぼう!」 共同生活の目標:「何事も心を込めてきちんと丁寧に作業する」 |
|
| 今回は春に行った味噌作りに続き、食品加工の第2弾として、コンニャク作りを行いました。普段は食材として身近なコンニャクですが、原料であるコンニャクイモはとてもアクが強く、煮ても焼いても食べることが出来ません。私たちがいつでもおいしいコンニャクを食べられるようになったのは、先人たちが苦労して試行錯誤(しこうさくご)し、加工方法を編(あ)み出してくれたおかげです。今回はコンニャク作りを通して、先人の工夫や努力に思いをめぐらせ、先人のすごさとありがたさを肌で感じてもらいたいと思い、上記のテーマを掲げました。 共同生活の目標は「何事も心をこめてきちんと丁寧に作業する」の2回目でした。第7ステージと同様に、1.清掃、2.食事、3.農作業・塾活動の3つの場面を特に意識して取り組んでもらいました。 |
|
| ■ 10月05日(金) 夜の集い | |
| ステージを始めるにあたって、塾頭よりお話がありました。 「今回はコンニャクイモを加工してコンニャクを作ります。コンニャクイモはアクが強くて、そのままでは食べられません。 |
|
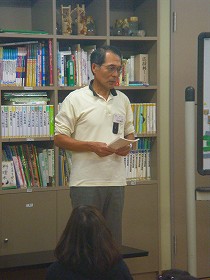 |
昔の人は色々と工夫して、食べられる方法を発見しました。どのようにすればコンニャクが食べられるようになるのか、実際に作りながら学んで下さい。そして、加工方法を発見した先人に、感謝の気持ちをもってほしいと思います。 食事の時、いつも『出されたものは全て残さず、よくかんで食べる』と言っています。みんな、よく食べられるようになりましたが、好きなものだけ食べたり、嫌いなものをお茶で流し込んだりする人がいるのが気になります。よくかんで、まんべんなく食べましょう。 |
| 先週、この塾の総合塾長が来られて『全てのものには命があり、助け合いながら生きている。命を大事にしてほしい。人は、一人では生きていけない。仲間がいるから生きていける。仲間を大事にしてほしい。』という話をして下さいました。 全ての食べ物は元々命があったもので、それを絶ちきって我々に生きる力を与えてくれています。だから、命を『いただきます』『ごちそうさま』と食事の度に必ず言うのです。姿勢を正してきれいに食べ、命をいただくことに感謝してほしいと思います。 残り少ない塾活動を有意義にするためにも、メリハリをつけて行動して下さい。」 |
|
| ■ 10月06日(土) 共同農園作業 ~トマトの片付け~ | |
| 夏の間、食卓に彩りを添えてくれたトマトですが、旬の時期が終わりを迎えました。今までの収穫に感謝をこめて、トマトを片付けました。 | |
 |
まずは、まだ実っているトマトを収穫しました。 熟していない青いトマトは、ジャムの原料になります。赤い実も青い実も、無駄にしないように、残さず収穫しました。 |
 |
収穫したトマトを集めると、青いトマトだけでバケツ3杯分になり、重さを量ると全部で12kgもありました。 その後、何人かの塾生が集めたトマトを選別しました。虫食いや痛んだ実が混ざっていないか一つ一つ確かめ、色や大きさごとに丁寧に分けていました。 |
 |
トマトを選別している間に、他の塾生たちはトマトを誘引しているヒモをほどきました。 ヒモがしっかり結ばれていて、なかなかほどけず苦戦しました。どうしてもほどけないヒモはハサミで切り、作業を進めました。 |
 |
 |
| ヒモが全てほどけたら、トマトと支柱を引き抜きました。 根が丈夫でなかなか抜けない株がいくつかありました。1人で抜けないトマトは、2人で「せーの!」と、力を合わせて引っ張っていました。 |
|
 |
そして、引き抜いた株や敷きワラ、雑草などを拾い集めました。 たくさんあったので拾うのに時間がかかり、塾生たちは暑さと長時間の作業で疲れていました。 トマトの株や痛んだ実は残さず拾い集めましたが、雑草や細かいワラを完全に拾いきることが出来ませんでした。 みんなは畑を見渡し、片付けきれなかったことが残念そうでしたが、ここで時間切れ。作業を止めて次の畑へ移動しました。 |
 |
普段、草取りをした雑草は畑の脇(わき)に捨てています。しかし、トマトの残さ(古い株や痛んだ実)は雑草と違い、畑に捨てると病気の原因となります。 片付けたトマトの株や痛んだ実は、塾生の体がすっぽり入るほどの大きな袋に、全て詰め込んで持ち帰り、塾庭の残さ置き場に捨てました。 |
| ■ 10月06日(土) 共同農園作業 ~秋野菜の世話~ | |
 |
 |
| トマトを片づけた後は、12ステージに植え付けた秋野菜(ブロッコリー、キャベツ、ハクサイ)の世話をしました。 1ヶ月の間で、秋野菜はグンと大きくなっていました。この調子で収穫まで無事に育つように、畝の上の細かい草を取り、追肥と土寄せをしました。 10月とは思えない暑さにみまわれて、トマトの片付けの疲れが残っていた塾生たちはヘトヘトになっていました。しかし、途中で投げ出さずに最後まで粘って作業していました。 |
|
| ■ 10月06日(土) 塾活動 ~コンニャク作り~ | |
 |
厨房に塾生全員が入ることはできないので、2チームずつに分かれて、講義とコンニャク作りを行いました。 コンニャク作りでは、まずコンニャクイモを洗う作業から始めました。コンニャクイモはアクが強く、素手で触るとかぶれてしまうので、ゴム手袋をして洗いました。 |
 |
 |
| 洗ったイモを細かく切り、水と一緒にミキサーにかけます。白っぽいどろどろの液体になりました。 | |
 |
ドロドロしたコンニャクイモを鍋に移し、火にかけて煮詰めました。 この時、焦げ付かないように絶えずかき混ぜ続けるのがポイントです。交代しながらかき混ぜていると、ドロドロした液体が少しずつ固まっていきました。 |
 |
鍋を火から下ろして、温度が60度になるまで冷ましたら凝固剤(ぎょうこざい)を混ぜ込みます。60度は手で触るには熱いので、軍手とゴム手袋を重ねてはめて作業しました。 凝固剤がまんべんなく混ざるように、よく混ぜ込みました。 |
 |
最後にバットに入れて、平らに形を整えました。 この時間の作業は、これで終わり。この後、冷えて固まったら「アク抜き」の作業が必要になります。 |
 |
コンニャク作りと並行して、食堂で講義を受けました。 講義では、コンニャクの歴史や食べられるようになる仕組み、食品加工と料理の違いについての説明がありました。 そして、「なぜ先人は、こんなに手間をかけて食品を加工をしようと思ったのか」をみんなで想像しました。 |
 |
「昔は食べるものがなくて、貯めておくために加工したんだと思う。」 「昔はスーパーがなくて買えなかったから、自分で作ろうと思ったのかな。」 「コンニャクイモを食べてみたらおいしくなくて、どうしたらおいしくなるか研究に研究を重ねたんだと思う。」 塾生たちは、先人の暮らしに思いをめぐらせ、次々と意見を出しました。 |
| みんなの意見をまとめた結果、「先人が食品加工をしたのは、身近な人の生活をより良くしたいという、思いやりの心があったためではないか。」という1つの答えが出ました。 塾生たちには、食品加工の技術だけでなく、思いやりの心も持ってもらいたいと思います。 |
|
| ■ 10月06日(土) 共同農園作業 ~オカボの収穫~ | |
 |
第4ステージに種まきしたオカボが、収穫の時期を迎えました。第7ステージにコムギを収穫した時と同様に、刈る人、刈った束を整える人、束ねる人の3人1組で作業しました。 今回の共同生活の目標を思い出し、一粒も無駄にしないように、丁寧に刈り取ることを意識して収穫しました。 |
 |
刈り取ったオカボを束ねる作業は、ヒモの締めが甘いと、せっかく束ねたオカボがバラバラになってしまいます。 スタッフにアドバイスをもらいながら、束を力いっぱいヒモで縛りました。だんだんコツをつかんできた様子で、「ギュギュッ」という音を鳴らせて、固く縛って束ねていきました。 |
 |
刈り取った後は、畑に落ちている穂や、残った草を拾いました。 細かいワラや草がたくさん落ちていて大変な作業でした。しかし、午前中のトマトの片付けで、最後まで片づけきれなかったことを思い出し、「今度こそ!」という気持ちで集中して取り組みました。 その結果、畑はとてもきれいになり、心を込めて取り組んだ結果が目に見える形となりました。 |
 |
 |
| 最後に、束ねたオカボを干しました。モロコシタロウ畑から1階のベランダまでリレー形式で運び、干しました。作業が終わるころにはすっかり日が暮れてしまいましたが、みんなで力を合わせて、全てのオカボを干し終えることができました。 このオカボは1ヶ月程度天日で干し、脱穀(だっこく)、精米(せいまい)してお米になります。このお米で、最終ステージに餅つきをする予定です。今から楽しみですね。 |
|
| ■ 10月06日(土) 夜の塾活動 ~卒塾アルバムの写真選び~ | |
 |
自然塾では、卒塾の記念にアルバムを渡します。そのアルバムの中に、チームの思い出やメンバーの紹介を書くページがあり、今回、そのチームのページを作り始めました。 まずは、今までの活動の写真を見ながら、ページに使う写真を選びました。 |
| ■ 10月06日(土) 夜の塾活動 ~コンニャク作りの続き~ | |
 |
卒塾アルバムの写真選びと並行して、昼間に作ったコンニャクの「アク抜き」の作業を見学しました。厨房ではスタッフが、固まったコンニャクをたっぷりのお湯でゆでていました。その様子を見学し、浮いてきたアクをおたまですくって取り除きました。 このあと、一晩水につけておきます。コンニャクが食べられるようになるまで、あと少しです。 |
| ■ 10月07日(日) 朝食 ~コンニャクの食べ比べ~ | |
 |
コンニャクがようやくできあがりました。朝食に、自分たちで作ったコンニャクを味噌田楽(みそでんがく)でいただきました。各チームのコンニャクが一切れずつ串に刺してあり、食べ比べが出来るようになっていました。 塾生たちはコンニャクを食べ比べながら、チームごとの味の違いや、売っているコンニャクとの違いなど、意見を言い合っていました。 |
| ■ 10月07日(日) 塾活動 ~卒塾アルバム作り~ | |
 |
土曜日の夜に引き続き、卒塾アルバム作りをしました。ページのレイアウトを考えて、文字を書いたり、選んだ写真を切って組み合わせたりしました。 各チーム、素敵なページが出来上がりそうです。 |
| ■ 10月07日(日) チーム農園作業 | |
 |
日曜日は雨だったので、満足に農作業することが出来ませんでした。各チーム、出来る限りの作業をしたり、畑の様子を観察して次回の計画を立てたりして過ごしました。 Aチームは、ゴマを収穫していました。株ごと畑から引き抜き、土間に立てかけていました。こうして乾燥させておくと、さやの中からゴマの粒が出てくるそうです。 どのぐらいのゴマがとれるのでしょうか。楽しみですね。 |
 |
 |
| Bチームは、ダイコンの間引きをしていました。間引きしたダイコンの葉は食べられます。 チームのみんなで持ち帰られるように、丁寧に包装していました。 |
|
| ■ 10月07日(日) ステージのまとめ | |
| ステージを終えるにあたって、塾頭からお話がありました。 「昨日は天気が良く、たくさん農作業が出来ました。少ない人数でしたが、みんな一所懸命取り組んでいましたね。粘り強さが見られて、感心しました。今日は残念ながら雨が降ってしまいましたが、自然には逆らえません。こういう時もあると思って我慢しましょう。 |
|
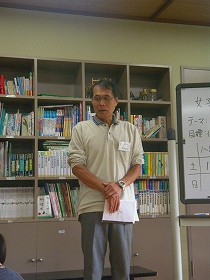 |
生きていく上で、我慢しなければならない場面は多くあります。その多くは、ちょっとした我慢で済みます。わがままを言いたい気持ちをぐっと抑えましょう。 昨日はコンニャクを作りました。コンニャクをはじめ、加工食品が出来たのは偶然ではありません。先人が生活の中で知恵を絞り、苦労し、工夫したから辿り(たどり)着いた結果です。我々はその恩恵を受けているのです。 先人の知恵に感謝しましょう。おじいさんやおばあさんなど、みんなの家庭を築いてきた人たちにも、感謝してほしいと思います。 |
| 毎年、この時期にノーベル賞が発表されます。受賞する人は、先人たちが積み上げてきた知恵を教わり、その上に新しい発見や最先端のアイデアを生み出しているのです。 頭の中だけで考えていても、良いアイデアは浮かびません。また、何でも他人任せでは、いい考えが浮かばず、生活もつまらないものです。自分で考え、工夫して、色々なことが出来るようになると、毎日が楽しくなります。自分から積極的に行動し、苦労にもチャレンジしてほしいと思います。」 |
|
| ■ 編集後記 | |
| 今回は運動会や学校行事と重なって、欠席や途中参加の塾生が多くいました。 しかし、一人ひとりが少ない人数をカバーしようと、農作業や共同生活を丁寧に頑張っているのが印象的でした。特に、頑張っている塾生ほど、楽しめているように見えました。 また、コンニャク作りでは、苦労を味わった塾生ほど、先人の苦労と工夫を想像することが出来て、先人の知恵に対してありがたみを感じたのではないでしょうか。 面倒なことや苦労が目の前にある時、「つまらない」と言ってサボったり面倒から逃げたりしても、つまらないままです。残り4ステージ、自分から積極的に活動に取り組み、心を込めて丁寧に取り組む楽しさを、少しでも塾生たちに体感してもらえるようにサポートしていきたいと思います。 K.K.
|
|
| ■ 食事メニュー | ||
| 金曜夕食 |  |
・ピラフ(ピーマン、パプリカ、ニンジン) ・ピーマンの肉詰めトマト煮スープ(ピーマン、トマト、ミニトマト) ・ピーマンカップポテトサラダ(ピーマン、ジャガイモ、ニンジン) |
|
|
||
| 土曜朝食 |  |
・ご飯 ・味噌汁(味噌、ナス、長ネギ) ・茶碗蒸し(栗、インゲン) ・オクラのベーコン巻き焼き(オクラ) ・ゴーヤの詰め物焼き(ゴーヤ、長ネギ) ・ゴーヤのポテト詰め焼き(ゴーヤ、ジャガイモ) ・ゴーヤのお浸し(ゴーヤ) ・モロヘイヤの和え物(モロヘイヤ) ・間引き菜のゴマ和え(間引き菜) |
|
|
||
| 土曜昼食 |  |
・栗ご飯(栗) ・すまし汁(ニンジン、ピーマン) ・秋刀魚の梅ショウガ煮(梅干し、ショウガ) ・ゴボウサラダ(ゴボウ、ニンジン) ・落花生豆腐(落花生、ショウガ) ・落花生おからの炒り煮(落花生、ニンジン、ピーマン) ・ネギ味噌(味噌、長ネギ) ・茹で野菜(間引き菜) |
|
|
||
| おやつ |  |
・栗の渋皮煮(栗) |
|
|
||
| 土曜夕食 |  |
・中華風炊き込みご飯(ゴボウ、ニンジン、ピーマン) ・中華風春雨スープ(長ネギ、ショウガ) ・麻婆ナス(ナス、ピーマン、パプリカ、長ネギ、ニラ、ショウガ、ニンニク) ・中華風もやしサラダ(ニンジン、キュウリ) |
|
|
||
| 日曜朝食 |  |
・ご飯 ・味噌汁(味噌、長ネギ、ジャガイモ) ・コンニャクの田楽(コンニャク、味噌) ・煮物(コンニャク、ゴボウ) ・五目豆(コンニャク、ニンジン、ゴボウ) ・インゲンのゴマ和え(インゲン) ・間引きカブのお浸し(間引きコカブ) ・漬物(からし菜) |
|
|
||
| 日曜昼食 |  |
・カレー焼きそば(ニンジン、ピーマン、パプリカ、ジャガイモ) ※希望チームは“そば飯”調理 |